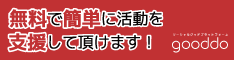今日は小学校のグラウンドに作られた特別コースにて、モトクロスバイク大会が開かれました。
少し前から練習の音が響いてきていて、村中の人が楽しみにしていた企画です。
こどもたちを連れて見に行ってみたら本当に村中の人が集まっていて大賑わいでした。

こんな感じでジャンプ台のような坂を飛び越えてレースをします。
プロテクターやヘルメットなども完備していて、かなり本格的です。
しかもなんと!この写真に写っている選手たちはこどもなんですよ!
一番小さい子はまだ7歳。女の子も混じっていてびっくりです。
同年代の子たちがレースしているのを見て、こどもたちは大盛り上がりでしたよ。

レースを見て戻ってきたこどもたちはすっかりバイクに頭が魅了されてまして、
みんな「ブーン!」といいながら走って移動してました。うん、きびきびしてよろしい。(笑)

さて、HOJではものすごく不思議なことが起きました。
電球を交換しようと思って、箱から出して置いておいたら、アルジェが見つけて遊び始めました。
そしてアルジェが手のひらの上に電球を当てるとなんと!電球が光るじゃありませんか!!
私やタケ、ジャンレの手だと光らないのに、アルジェだと光ります。なんですかこれ?静電気?

写真じゃ信用できないでしょうから、ぜひショートムービーもご覧ください。トリックではありません!
よく私はふざけて「疲れたー、バッテリーが切れたー、アルジェ、充電させてー」と言って
アルジェに抱きついているんですが、まさか本当に充電できていたとは。(笑)
みなさんもバッテリーが切れたら、ぜひアルジェに会いに来てくださいね!
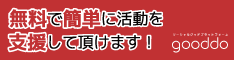
こんばんわタケです♪
今日は小学校が午後から休校ということで、アツシ発案による子供達と何かゲームをして遊ぼうということになりました。
何をするにしても勝者にはご褒美をあげることでゲームが一層盛り上がると思い、アツシがお菓子を市場から買ってきてくれました。
ところが子供の嗅覚はすごいです!
まだ何も言ってないのにお菓子を買ってきたのをすぐ察っしたのかおねだりしてきます(笑)

ゲームの勝者にあげるからね♪と言ってるのにどうしても今食べたい様子(笑)
まぁそんなこともあり、今日は何かをしようといことで公園に行きました。
そこで行われたものがティクソという遊びです。

この遊びのルールは二手のチームに別れ、お互いの陣地を守りながら相手の陣地に触るというゲーム!
相手の陣地を取りに行くため、自分の陣地から離れた人は相手チームに触られたら捕まり、さらにその捕まる条件は自分より後に陣地を離れた相手チームの人のみにしか捕まりません!
…….あ〜〜文字で説明するのがすごく難しい!!
自分でこの文章読んでて本当に意味わかりません!!
説明下手でごめんなさい(笑)

とにかくスポーツでいうカバディに近いです。
しかしこれはよくできている遊びで、大人が参加しても超楽しい!!しかも公園がいい障害になってくれてアスレチックティクソになっています。
HOJ以外の子供達も一緒に参加し、大盛り上がり↑↑↑

RJボーイもこんな感じです!
HOJで子供達と遊ぶ際はオススメできる遊びですね♪
そういえば結局お菓子がどうなったかというと、みんなとても盛り上がったし、もう全員が勝者でいいや♪
ってことで子供達みんなにお菓子をあげました(笑)
いや〜アツシはとても優しいです。
平和でいいですね〜めでたし、めでたし♪
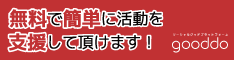
元ボランティアスタッフのアツシが立ち上げた「サンロケ小学校特別支援学級創設プロジェクト」。
名前が長いですね。教室につける名前を取って「MIRAIクラスプロジェクト」と呼ぶことにします。
(プロジェクトの詳細は前回のアツシの投稿をご覧ください)
日本で支援者を募り、目標額を集めたアツシがHOJに戻ってきました。
さっそく約束の建設資金を校長先生に届けに行きました。ご支援くださったみなさん、ありがとうございます!

アツシの来訪に合わせて、学校では学習障害のこどもたちの調査を実施しました。
まずは保護者を集めて説明会。こういうプロジェクトには保護者の理解と協力が欠かせません。
今回は15人のこどもが調査対象として選ばれているのですが、その半分以上がイスラム教の家庭です。
1990年代まではこの地域のイスラム教徒たちは公教育を受ける機会がなかったので、
今学校に通っている子たちの親世代には、読み書きができない人がとても多いんです。
親が読み書きできないと、こどもの勉強を手伝うことができないので、
どうしてもこどもの勉強にも遅れが出てしまう、ということのようです。
それが巡り巡って差別や分断につながってしまう悪循環を、なんとか断ちたいですね。

調査に協力してくれたのは、他校で学習障害の子たちを専門に教えている4人の先生たち。
1人ずつのこどもを面接し、文字は読めるのか、色や形は認識できるか、数字はどうか、
コミュニケーション能力はどうか、長時間座っていられるか、
指示を理解したり記憶したりできるかなどを、かなり細かく調査します。
同時に親への聞き取り調査も行い、家庭でのこどもの振る舞いも知ることで、
より正確にその子の実情を把握することに努めます。

1日がかりで調査をした結果、15名全員が「特別な支援が必要」ということになりました。
1人ずつについて詳細なデータを得たので、今度はそれを担任の先生たちが精査した上で、
1人ずつに対して指導案を作成し、それを教育省に提出して認可を受ければ、
晴れて特別支援学級をスタートすることができます。
それらの事務作業にこれから数週間はかかりそうですが、7月中旬には授業を始められる見込みです。

調査の様子は動画にもまとめたのでぜひご覧ください。
こんなに教育熱心な先生たちがいるんだ!と嬉しくなりますよ。
このプロジェクトには、ハウスオブジョイあてに寄付していただいた、
さだまさしさんの「風に立つライオン基金」からの支援金の一部も充てさせていただきました。
今後も給食プロジェクトと併せて、じっくりと育てていきたいと思います。
応援よろしくお願いします!